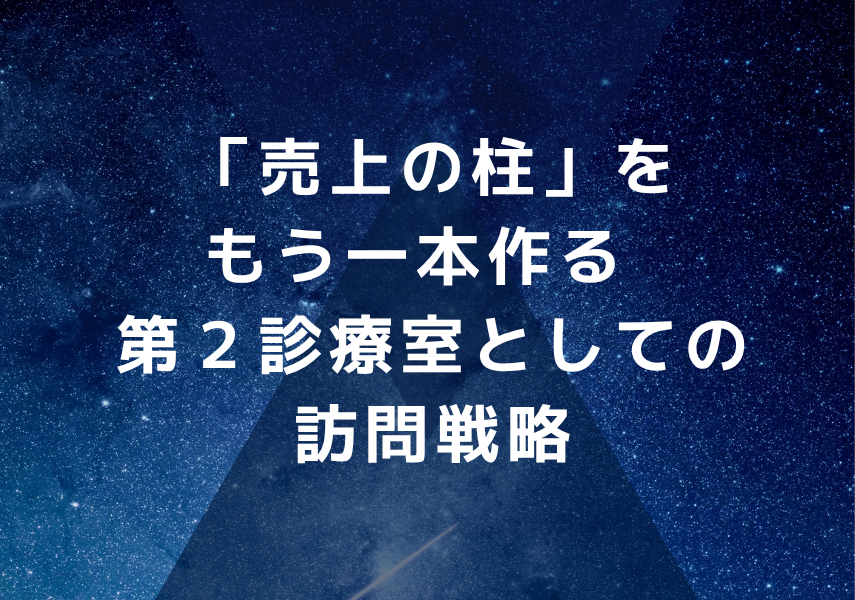
「売上の柱」をもう一本作る ― 第2診療室としての訪問戦略
目次
1.なぜ今、訪問歯科なのか?
歯科経営の構造変化と第2の柱の必要性
現在、多くの歯科医院が「外来診療だけでは先が見えない」という共通の課題に直面しています。地域の高齢化、患者数の自然減少、人材不足、診療報酬の抑制──こうした要因が複雑に絡み合い、これまでの「待つ歯科経営」は限界を迎えつつあるのです。
一方で、訪問歯科診療という選択肢には、まさにこの構造的変化への実践的な解が含まれています。「売上の柱をもう一本作る」という戦略的発想のもと、訪問歯科を「第2診療室」と位置づけることで、外来依存からの脱却と、持続可能な地域医療への貢献の両立が可能になります。
外来一本足経営の限界
高齢化が進む地域では、定期的に来院していた高齢患者が、ある日を境に来られなくなります。脳卒中、認知症、骨折、慢性疾患──理由は様々ですが、こうした「フェードアウト」は今や珍しくありません。
厚労省の調査では、2024年時点で全国民の約3人に1人が65歳以上、高齢者の5人に1人が認知症という予測も出ています。つまり、「通院できないが、診療は必要」という患者が爆発的に増加しているのです。 外来に通えなくなった患者をそのまま失ってしまうのか、あるいは訪問によって関係を継続するのか──この差が、将来の医院経営に大きな違いをもたらします。
患者数の減少は「通院困難層」の増加でもある
患者数の自然減少は避けられませんが、実はこれは「市場の縮小」とは言い切れません。通院できなくなった高齢者、その家族や介護者、医科・介護職とのネットワーク──それらに支えられる形で、新たな患者層が生まれているのです。
訪問歯科は、こうした「通院困難層」にアプローチする唯一の手段であり、しかも彼らは口腔管理や口腔リハビリ、食支援など継続的なサポートを必要とする「ストック型」の対象者です。つまり、単発の来院よりもLTV(生涯価値)が高く、医院の経営を安定させる新たな柱となるのです。
訪問診療は「点」ではなく「線」で広がるビジネスル
訪問診療を単なる「応急処置」と捉える時代は終わりました。現在の訪問歯科は、口腔ケア、リハビリ、食支援までを含めた「生活機能支援」の一環として位置づけられています。これは、1回限りの治療で終わる「点」ではなく、患者との継続的な関係性の中で構築される「線」または「面」のビジネスです。 例えば、ある高齢患者に対して訪問診療を開始すると、その家族や介護者との関係性が生まれます。そして、次第に他の利用者、ケアマネジャー、医師、施設職員とのつながりへと拡大していきます。このようにして「地域連携のネットワーク」が構築され、紹介が紹介を呼ぶという良循環が始まるのです。
2.「第2診療室」の意味とは?
外来と並ぶ、戦略的な訪問部門の設計
訪問歯科を単なる「外来の延長」や「副業的な取り組み」と考える時代は終わりました。むしろ、今後の歯科経営において、訪問部門は外来に並ぶ“第2診療室”としての戦略的ポジションを担います。 この章では、「第2診療室」としての訪問歯科をどのように位置づけ、どう機能させていくべきか。その設計思想と運用モデルを解説します。
「応急処置」ではなく、「継続的な診療システム」へ
かつての訪問診療は、いわゆる「往診型」であり、緊急時や家族の要請による単発の処置が中心でした。これは“点”の医療であり、収益にも患者関係にも持続性が乏しいものでした。
しかし現在の訪問歯科は、介護保険や医療連携を背景に「生活支援型」「予防・管理型」へと進化しています。診療計画を立て、月単位・年単位で継続フォローする“線”の医療です。つまり、ストック型ビジネスとして成立するのです。 「義歯調整をして終わり」ではなく、「口腔管理→食支援→リハビリ」へとつながるルート設計こそが、第2診療室の本質です。
第2診療室は“外にある”
新しい市場への入口
第2診療室の特徴は、「医院の外にある」ということです。外来のように“患者が来る”のではなく、こちらが“患者の生活の場に行く”という逆の構図。
この構造がもたらす最大の強みは、自院ではリーチできなかった患者層にアクセスできることです。例えば:
- 外来に通っていた高齢患者の「通院困難化」後も関係を維持できる
- 高齢者施設、在宅ケアのネットワークから“新患”を獲得できる
- 家族や介護職、医科との関係性を通じて外来患者にも波及する
訪問は単に「患者を診に行く」だけではなく、「新しい市場への出入口」としても機能するのです。
ストック型収益構造が生む安定性
訪問歯科のもう一つの利点は、先読み可能な収益構造です。定期訪問のスケジュールがあらかじめ決まっており、患者との関係も長期化するため、数カ月先の売上が見通せます。
これは、日々の新患数やキャンセルに一喜一憂する外来とは異なり、事業としての投資判断がしやすくなるという経営的メリットを生みます。
- スタッフ採用や人件費の見積もり
- 設備投資の回収計画
- 増患戦略や地域連携の中長期計画 など
経営の安定と戦略的拡大、双方を可能にするのが「訪問を第2診療室に据える」という考え方です。
外来と訪問が支え合う「二診体制」へ
第2診療室としての訪問診療が安定してくると、外来との相乗効果も見込めるようになります。
- 訪問患者の家族が、外来に紹介される
- 地域での認知度が上がり、新患が増える
- 医科やケアマネとの連携が、外来の診療にも良い影響を与える
つまり、訪問が独立して稼ぐだけでなく、外来を下支えし、強化するエンジンにもなっていくのです。
次章では、実際にこの「第2診療室=訪問歯科」をどのように導入し、継続的に仕組化していくのか。その具体的なステップを5段階に分けてご紹介します。 訪問導入を迷う時期は終わり、設計し、実行に移す時です。
3.成功する訪問歯科の5つの仕組み化ステップ
導入から安定運用までの実践フレーム
訪問歯科診療を成功させるには、「なんとなく始める」のではなく、設計図をもって段階的に組み立てていくことが欠かせません。 ここでは、これまで数多くの歯科医院で成果を上げてきた、日本訪問歯科協会推奨の“5ステップモデル”を紹介します。導入初期の医院から、すでに取り組んでいるが伸び悩んでいる医院まで、すべてのステージに適応できる実践的な構造です。
ステップ1:現状分析
始める前に、まず「知る」
最初のステップは、「なんとなく訪問診療をやってみよう」ではなく、自院の可能性と制約を可視化することです。
- 自院の地域に、通院困難な高齢者はどれくらいいるか?
- 外来患者の中に、訪問の対象になり得る人はいないか?
- スタッフに訪問への関心・適性があるか?
- 収支モデルとして成り立ちそうか?
特に重要なのは「自院の強みをどこに生かすか」を明確にすることです。訪問は“誰でも同じ結果が出せる分野”ではなく、得意分野や関係性の築き方に応じてカスタマイズすべき分野です。
ステップ2:院内体制の構築
小さく始めて、大きく育てる
「人がいないからできない」は、よく聞きますが、多くの場合は“ゼロから完璧を目指す”思考が原因です。
- 週に1回、1人の歯科医師が2時間だけ訪問する
- 非常勤の歯科衛生士を1名だけ巻き込む
- 準備や記録は、外来スタッフがサポートする
このように、「今あるリソースで最小構成の訪問体制」をつくるのが最初のゴールです。突発的な患者に対応するフロー型ではなく計画的に患者に対応するストック型の訪問体制にするには、小さくても「継続できる仕組み」が欠かせません。
ステップ3:集患と関係づくり
信頼がすべてを動かす
訪問歯科の集患は、「信頼関係」がものを言います。
- 外来患者やその家族からの転換
- ケアマネジャーとの連携と信頼構築
- 地域包括支援センター、居宅介護事業所とのつながり
- 施設への丁寧なヒアリングと初期対応
特にケアマネジャーとの関係性は要です。“紹介したくなる歯科医院”になるために、どんな情報提供をすべきか、どう説明すると安心してもらえるかを設計しましょう。
ステップ4:訪問診療の最適化
外来と同じでは成果が出ない
訪問先では、外来とは異なる制約が数多くあります。
- 医療器具の制限
- 対応できる疾患や診療行為の選択
- 医科との連携や家族への説明フロー
- バリアフリー環境ではない現場での対応
これらを理解した上で、「どこまで対応するか」の線引きと、「誰が何を行うか」の役割分担を整理することが必要です。
さらに、患者に「ここまでやってくれるのか」と思ってもらえるような“プラスアルファ”の提供(例:食支援や口腔リハ)を持っておくことが、継続率や紹介数に直結します。
ステップ5:医療事務と請求業務の整備
利益を残すには“算定力”が鍵
訪問診療は医療保険・介護保険の両方を扱うため、請求事務の難易度が上がります。特に注意すべき点は次のとおりです。
- 医療と介護の請求対象の違い
- 同一建物/単一建物の考え方
- レセプト記載のルール
- 文書提出のタイミングと内容
多くの医院が「知らないことで損をしている」現実があります。請求知識のアップデートと、院内での情報共有体制の構築が、収益の安定化に直結します。
まとめ:仕組みをつくれば、再現性が生まれる
訪問歯科を本格導入した医院の多くが、最初は手探りでした。しかし、この5つのステップを押さえれば、「行き当たりばったり」ではなく「再現可能な成果モデル」として成長できます。
そして次章では、仕組みを整えたことで得られる経営面のメリット――「安定収益」「外来との相乗効果」「信頼の獲得」――について、具体的な成果とともに掘り下げていきます。
4.訪問導入による3つの経営的メリット
安定・信頼・成長をもたらす新しい診療部門
訪問歯科診療を導入することは、単に「収益が増える」だけではありません。医院経営全体にとって、中長期的な安定と成長の基盤を築く効果があります。
この章では、訪問診療を“第2診療室”として育てることで得られる、3つの経営的メリットを具体的に紹介します。
1.【収益の安定】先が読める“ストック型”収入
訪問歯科の最大の特長は、「通院できない患者に対して、計画的・継続的に診療する」という点です。
これはつまり、来院型の外来とは異なり、患者が診療予定に沿って“待っていてくれる”ということを意味します。事前にスケジュールが組まれ、一定の頻度で診療が繰り返されるため、以下のような経営的利点があります。
- 月次・四半期単位での収入予測が立てやすくなる
- 外来の予約状況に左右されない売上構造
- 採用や設備投資など、計画的な経営判断が可能に
特に「外来が空いている時間を訪問にあてる」といった運用は、時間資源を最大化する働き方改革の一環にもなります。
2.【地域内評価の向上】“信頼”が患者を連れてくる
訪問歯科診療では、外来では接点のない“第三者”との関係が生まれます。たとえば…
- 介護職員・ケアマネジャー
- 医科の主治医・訪問看護師
- 家族・ヘルパー・地域包括支援センターの職員
こうした多職種・多層の関係者との協働の質=医院の評価となって地域に広まっていくのです。
訪問診療を通して得た信頼が、「あそこの歯科医院は、安心して紹介できる」「現場に強い」といった“口コミ的広報”を生み、以下のような波及効果をもたらします。
- 外来患者の家族が受診する
- 医療機関からの紹介が増える
- 施設職員やケアマネが“患者”になるケースも
つまり、訪問の質を高めることは、医院ブランドの強化そのものであり、外来の新患増にも直結します。
3.【成長の持続】院内の学びと組織力を育てる
訪問歯科は、診療技術だけでなく、コミュニケーション力・観察力・全身管理への配慮といった、多面的な力を求められます。
その結果、関わるスタッフが次のような力を身につけ、医院全体のレベルアップが起こります。
- 歯科衛生士:予防や口腔ケアの知識を現場で実践し、成長機会が増える
- 医療事務:介護保険請求や書類作成など、専門スキルが蓄積される
- 歯科医師:高齢者医療の知識が深まり、医科との連携スキルが磨かれる
また、訪問診療では多職種連携がほぼ必須のため、“一人で完結しない働き方”が自然と定着していきます。これは、医院組織を“属人化”から“チーム化”へと進化させ、経営の持続可能性を高める要素になります。
まとめ:第2診療室が“経営体質”を変える
訪問歯科の導入は、単に“売上アップの施策”にとどまるものではありません。それは、医院経営の構造を「外来依存型」から「分散・安定型」へと変える変革の一手です。
- 収入の安定
- 評判の向上
- 組織の成長
この3つの視点を意識して訪問歯科に取り組めば、医院は“選ばれ続ける存在”へと進化していきます。
次章では、実際にその進化を実現した歯科医院の事例をご紹介します。理論を超えたリアルな現場の工夫に、ぜひご注目ください。
5.事例に学ぶ:外来主体からの転換成功例
小さな一歩が医院を変えた3つのケース
「訪問歯科を導入すべきなのはわかっている。でも、うちのような小規模医院では難しいのではないか」
そう感じている先生も多いことでしょう。
しかし、成功している医院の多くも、最初は同じような不安や疑問からのスタートでした。
この章では、外来主体の経営から訪問歯科へと舵を切り、成果を上げた3つの実例をご紹介します。いずれも特別な設備や人材があったわけではなく、仕組みと工夫で道を切り拓いたケースです。
事例①:“計画診療”へシフトし、月15人のストック患者を獲得
【東京都・個人歯科医院・院長+DH1名】
この医院では、これまで高齢患者からの依頼を受けたときだけ「往診」として対応していました。内容は義歯調整や抜歯などの応急処置が中心。月に1~2件程度の依頼に対応するのみで、訪問診療という認識すら曖昧でした。
転機となったのは、日本訪問歯科協会のセミナーに参加したこと。
「訪問は“都度対応”ではなく、“継続診療”として組み立てられる」という視点を得た院長は、患者ごとに訪問計画を立て、口腔ケア・管理に移行する仕組みをつくりました。
その結果、定期訪問患者は半年で15人を超え、月20回以上の訪問診療を安定的に運用できるように。以前は使われていなかった午後の時間が、今では大きな収益源となっています。
事例②:ケアマネ3人と信頼関係を築き、新患紹介が倍増
【愛知県・郊外型医院・スタッフ4名】
この医院は、かつて外来患者の減少に悩んでおり、「地域連携の強化」を目指して訪問歯科の導入を検討しました。最初の課題は、「患者がいない」「どこから始めたらよいか分からない」という状態。
まず行ったのは、地域包括支援センターへの訪問と、ケアマネジャー向けのミニ勉強会の開催でした。テーマは「お口の乾燥とう蝕」「口腔ケアで防げる誤嚥性肺炎」など、実務に直結するものを選び、無理に患者紹介を求めない姿勢を貫いたことが功を奏しました。
3ヶ月で3名のケアマネジャーとの関係が深まり、そこから自然な形での患者紹介が始まりました。結果として、初年度の訪問患者数は月平均2名から8名へと増加。
「誰にでも紹介できる安心感がある」という信頼が、“安定的な新患供給”という資産になりました。
事例③:訪問導入後、外来新患数が前年比120%に
【福岡県・住宅地立地・院長40代】
「外来の患者数が減ってきたので訪問を始めたら、逆に外来が増えた」――この逆説的な成果を生んだ医院もあります。
この医院では、地域の施設や訪問先での診療姿勢が評価され、その評判が外来へと波及。訪問患者の家族が「今度は自分の治療をお願いしたい」と来院するケースが月に数件ありました。
さらに、訪問先のケアマネジャーや看護師が家族を連れて来るようになり、口コミによる外来新患が前年比120%に。
この医院の特徴は、“訪問と外来を分けない運用”。「医院全体で生活支援に関わる」という意識がスタッフ全体に浸透し、結果として医院全体のブランド力が上がった事例です。
まとめ:成功の鍵は「小さく始めて、大きく育てる」
訪問歯科の導入は、決して大規模な投資や人材がなければできない取り組みではありません。今回紹介した事例に共通するポイントは、以下の3つです。
- 最初から“完璧”を目指さず、できる範囲で始める
- 継続診療として“仕組み化”を意識する
- 信頼関係の構築を何よりも優先する
次章では、こうした成功事例の共通項を踏まえ、訪問歯科を未来につなげていくための「まとめ」として、導入の着眼点を整理します。医院の未来を見据えた“第2診療室”の持つ可能性を、改めて確認していきましょう。
6.まとめ:訪問歯科は「未来への投資」
“迷い”を“構想”に変えるとき
ここまでの記事では、訪問歯科診療を「第2診療室」として位置づける意味、その導入と運用のステップ、そして実際に成功した事例を紹介してきました。
経営環境が不透明な時代において、訪問歯科は単なる“目先の売上確保策”ではありません。それは、医院の経営体質そのものを強化し、未来に向けて地域とともに歩むための“投資”です。
「待つ」だけでは通用しない時代へ
人口減少、超高齢化、診療報酬の抑制――これらは、すべて外来偏重型経営の限界を突きつけています。
一方で、介護・医療が生活の場へと移行する中、訪問歯科のニーズは着実に増えています。
重要なのは、「患者が来なくなった」ではなく、「患者が“行けなくなった”」という現実です。
訪問診療は、この“取りこぼし”を防ぎ、関係を継続する唯一の手段です。
収益・信頼・組織力──三位一体の成果
訪問歯科の導入は、以下のような複合的な成果をもたらします。
- 【経営】 継続的な診療モデルによるストック型収入の実現
- 【評判】 地域連携による医院ブランドの向上と外来患者の増加
- 【組織】 チーム医療を通じたスタッフの成長と定着率の向上
これらは、いずれも“時間”をかけて積み上がっていくものです。だからこそ、訪問歯科は「未来への投資」と言えるのです。
始めるハードルは“情報と設計”で越えられる
「うちは人が足りない」「訪問経験がない」「請求が難しそう」――
こうした不安は、導入前のほとんどの歯科医院が抱えているものです。
しかし、今は訪問診療の導入支援、研修、請求サポート、地域連携のノウハウなど、実務を補完する仕組みが整いつつあります。
重要なのは、“できない理由”を探すことではなく、“どうすればできるか”を設計すること。
小さく始めて、大きく育てる。そのための道筋は、すでに多くの医院が歩んでいます。
最後に:歯科医院が「地域の医療ハブ」になる未来へ
訪問歯科診療は、単なるサービスの追加ではなく、医院の存在意義を問い直し、再定義する試みでもあります。
患者にとって、自分の生活圏に「歯のことも相談できる人がいる」
地域にとって、「あの歯科医院がいざというとき来てくれる」
そう思われることが、10年後のあなたの医院を支える礎となります。
歯科医院が“地域医療の最後の砦”であるために、今、訪問歯科を「経営の未来」として、真剣に構想してみてはいかがでしょうか。
それはきっと、あなたと地域の両方にとって、かけがえのない投資となるはずです。
書籍『数値化の鬼』の要約解説図をプレゼント!
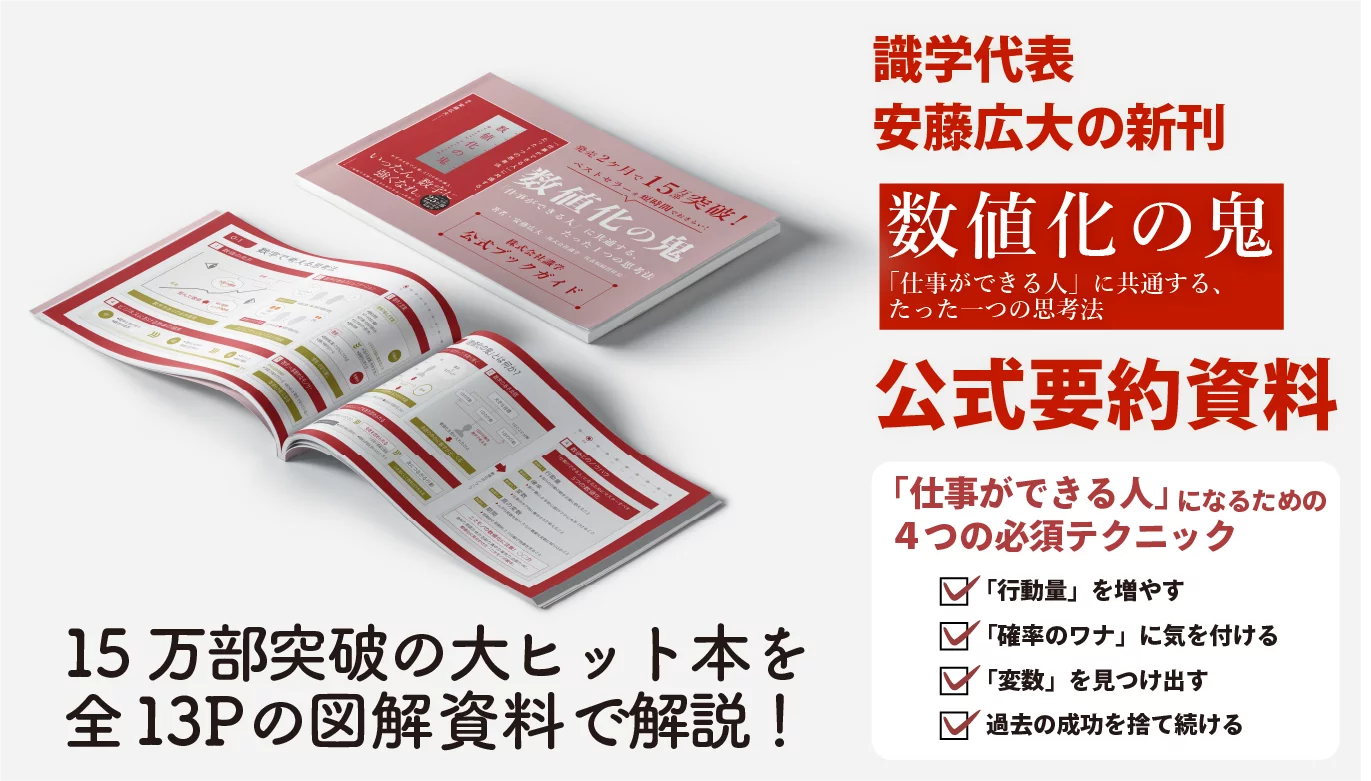
株式会社識学 代表取締役社長 安藤広大の執筆した書籍『数値化の鬼』が、なんと発売後 約1か月で12万部を突破しました!
この感謝を皆様にも還元すべく、株式会社識学では、『数値化の鬼』の図解解説資料を作成いたしました!
一度書籍をお読みになった方も、まだお手元にない方もどなたでも満足いただける完成度となっています!
眺めるもヨシ、印刷して目の付くところに飾るもヨシ、使い方は自由自在!
是非、こちらからDLしてくださいね!
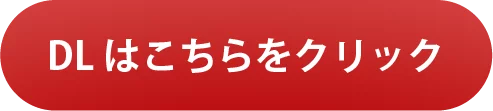

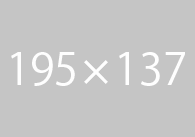
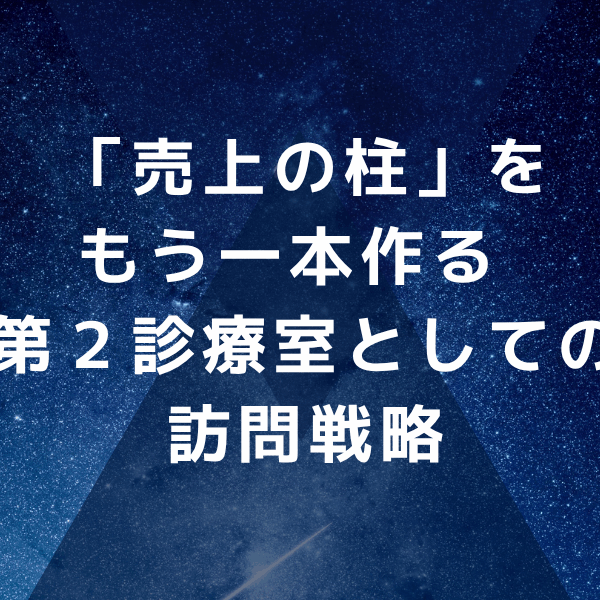
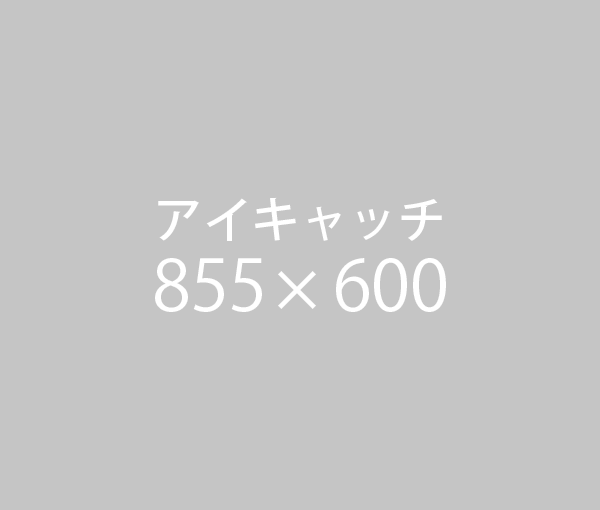

この記事へのコメントはありません。