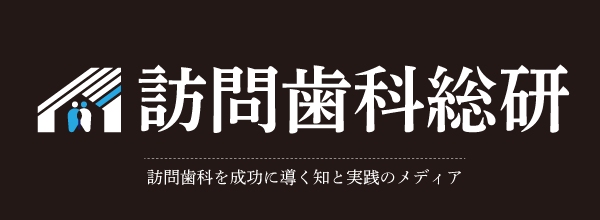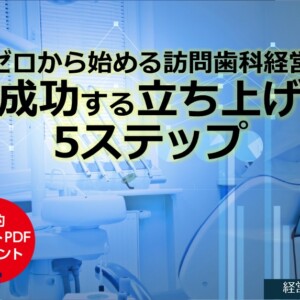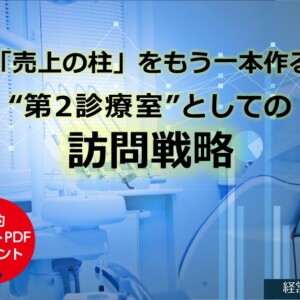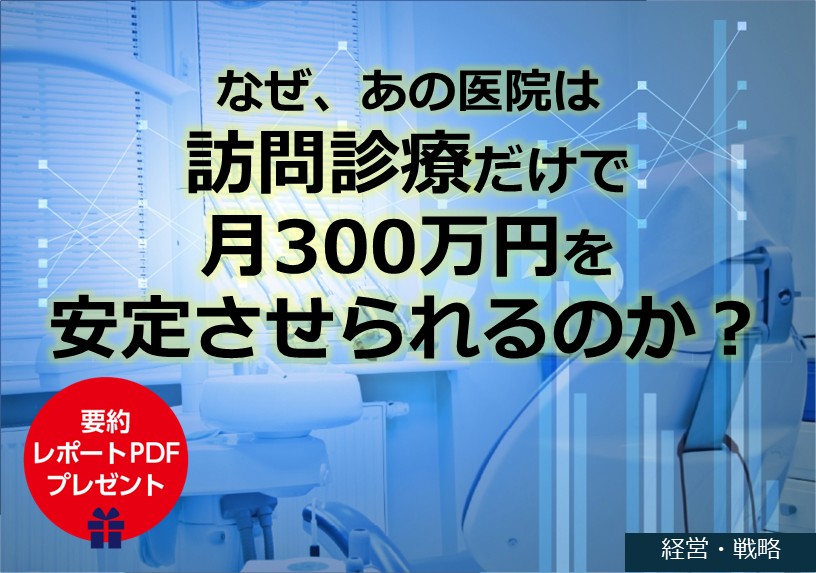
なぜ、あの医院は訪問診療だけで月300万円を安定させられるのか?
目次
1.なぜ今、訪問診療に本気で取り組むべきなのか
「もう、これ以上は無理かもしれない」
「これ以上、患者数を増やすのは難しいんです。スタッフがもう限界で…」
この言葉は、ある中堅歯科医院の院長先生が、ふと漏らした本音です。
決して経営が苦しいわけではありません。むしろ外来は順調で、予約も埋まり、リコール率も高い。
けれど、これ以上の成長を目指そうとすると、スタッフの残業が増え、気力も体力も持たなくなる――そんな“成長の限界”を肌で感じていたそうです。
この医院がたどり着いた答え。それが「訪問診療の本格導入」でした。
“頑張って詰め込む成長”の限界
近年、歯科医院を取り巻く環境は大きく変わってきました。
外来診療の単価は頭打ち傾向
材料費・人件費は右肩上がり
スタッフ確保や定着は年々難しくなり
「患者を増やす=負担も増える」構造に
成長しようと努力を重ねれば重ねるほど、医院の中の人が疲弊していく。
それが、いま多くの歯科医院が抱えるジレンマです。
訪問診療は「負担を増やす方法」ではなく、「役割と時間を再設計する方法」
このような状況の中で、訪問診療は「ただ仕事を増やす」ための手段ではありません。
むしろ、“外来以外の時間と人の配置を見直す”ことで、医院全体の運営効率を上げ、無理のない成長を実現する方法です。
成功している医院に共通するのは、次のような発想です。
- 外来とは別に「訪問専用の時間帯・曜日」を設定する
- スタッフを兼務ではなく「役割別」に分ける
- 訪問先を曜日ごとに固定し、ルーティン化する
- 点数・収益を“施設単位”で設計して無理なく回す
つまり、訪問診療は、医院の中で頑張って詰め込むのではなく、地域に“もうひとつの診療室”を持つという発想で運営されているのです。
スタッフが疲弊しない“成長の形”がある
訪問診療がスタッフにとっても負担が少ない理由は、いくつかあります。
- スケジュールが固定化され、突発対応が少ない
- 「今日何をするか」が明確で動きやすい
- チームで動くため、分担と連携が自然にできる
- 患者や家族からの感謝を受けやすく、やりがいがある
- 外来よりも患者数が少なく、1人ひとりにしっかり関われる時間がある
つまり、訪問診療は“忙しい”かもしれませんが、“消耗する忙しさ”ではなく、“やりがいある充実”につながる働き方なのです。
成長の選択肢を「医院の外」に持つということ
これからの歯科医院は、「外来を頑張るか、諦めるか」ではありません。
選択肢はもっと広く、「医院の外に診療室を持ち、外来と訪問の両輪で成長する」という未来があるのです。
訪問診療は、単なる補助収入ではありません。
効率・継続性・社会的意義を兼ね備えた、医院経営の“第2のエンジン”です。
そして今、そのエンジンをどう設計するかが、これからの医院の成長力を決めていきます。
次章では、実際に訪問診療を第2の診療室として確立し、月300万円を安定して生み出している医院の具体事例をご紹介します。
2.「偶然の成功」ではなかった――月300万円を達成した医院の背景
訪問だけで月300万円の安定収入
「うちは訪問だけで、毎月300万円ほど安定しています」
そう語ってくださったのは、関東近郊で訪問診療を本格的に展開しているA歯科医院の院長先生です。
その言葉を聞いた多くの先生方が、こう思われるかもしれません。
「立地が良かったんじゃないか」「たまたま良い施設とつながれたんだろう」と。
しかし実際にお話を伺うと、それが“偶然”ではなく、極めて“戦略的に築かれた成果”であることが見えてきました。
本章では、このA医院の背景をもとに、訪問診療で成果を出す医院に共通する構造を明らかにしていきます。
スタート時の状況――小さく、しかし確信をもって始めた
A医院が訪問診療を始めたのは、開業から5年目のことでした。
外来は安定しており、大きな問題もなかったものの、「これ以上、診療台やスタッフ数を増やすことなく、成長できる方法はないか」と模索していた時期だったそうです。
訪問を始めた当初は、週1日・半日のみ。1人の歯科医師と歯科衛生士の2名体制で、1件のグループホームを訪問するところからのスタートでした。
「まずは“第2の診療室”を1つだけ持つつもりで始めました」と院長先生は話します。
医院の強みを“外に展開する”という発想
A医院が特徴的だったのは、訪問診療を“全くの別物”として考えるのではなく、すでにある医院の強みをそのまま外に持ち出すという発想で取り組んだことです。
たとえば、
- スタッフの患者対応マニュアルを訪問用にも転用
- カルテやスケジュール管理も外来と同じレベルで整備
- 補綴の説明や同意書も丁寧にセット化して準備
このように、医院の「診療品質」と「運営の整備力」を、そのまま訪問の現場でも再現する体制を整えていました。
その結果、施設側からの信頼も得やすく、他の施設からの紹介にもつながっていきました。
「第2の診療室」として独立運用したことが安定のカギに
収益が安定してきたタイミングで、院長先生は訪問診療を明確に“第2の診療室”として独立運用する決断をされました。
- 訪問診療専任の歯科医師を1名採用
- 訪問専属のコーディネーターを配置
- 曜日ごとにエリアと施設を固定し、ルートを最適化
これにより、「誰が・どこで・何をするのか」が明確になり、医院全体としての効率が大きく向上しました。
この時期に特に注力したのが「診療スケジュールの標準化」と「請求体制のWチェック体制(レセコン入力+外部の医療事務レセプト点検担当者(訪問歯科に詳しい医療事務経験者)との連携)」でした。
この仕組みが整ったことにより、月ごとの収益のばらつきが減り、毎月300万円前後の安定収入を確保できるようになったのです。
院長の言葉:「成功は仕組みの上に成り立つ」
「訪問診療で結果が出ている医院は、特別なことをしているわけではありません」と、院長先生は言います。
「ただ、最初から“第2の診療室”として向き合い、スタッフと一緒に“再現できる仕組み”をつくることに集中しただけです」。
逆に言えば、訪問診療を“場当たり的”に行っていたら、途中でうまくいかなくなっていたとも振り返っておられました。
訪問診療で成果を上げることは、決して偶然ではありません。
明確なビジョンのもと、小さく始め、着実に仕組みを整えることで、「医院のもう一つの診療室」として機能させることができるのです。
次章では、こうした成功医院に共通する「訪問診療の収益構造」について、具体的な数字と構造をもとに解説していきます。
3.訪問診療の“収益構造”を分解する
第2の診療室として安定収益を生むには
訪問診療に取り組もうと考えたとき、院長先生が最初に知っておくべきことの一つが、「収益のしくみ」です。
外来とはまったく異なる構造を持つ訪問診療では、単価や件数、時間の使い方によって収益が大きく変わってきます。
本章では、歯科訪問診療における算定ルールに基づいて、実際にどのように“第2の診療室”として安定した収益を確保できるのかを考えていきます。
収益は「点数 × 患者数 × 稼働日」で構成される
訪問診療の収益は、大きく次の3要素で決まります。
- 1人の患者に対して算定できる診療報酬(点数)
- 1日あたりに診療できる患者数(件数)
- 月間の稼働日数(頻度・曜日の固定)
日本訪問歯科協会の調べによると、口管強、歯援診1のとき、介護保険施設で9名の患者さんを1日で診療した場合、患者1人あたりに対して平均1,300点が、高齢者施設で9名なら1,200点、居宅で1名なら2,100点が算定できます(診療報酬点数表・令和6年度改定版に基づく)。
たとえば、ある月の訪問で以下のような患者対応を行った場合:
介護保険施設で9名に対して、月に4回、2施設に対して診療
1,300点 × 9× 4× 2=93,600点
1施設当たり所要時間は、20分×9=180分=3時間
準備等で3時間30分かかると見積もれます。
総所要時間は、3.5時間×4×2=28時間
高齢者施設で9名に対して、月に2回、8施設(有料老人ホーム:3、サ高住:3、グループホーム:2)に対して診療
1,200点 × 9× 2× 8=172,800点
1施設当たり所要時間は、20分×9=180分=3時間
準備等で3時間30分かかると見積もれます。
総所要時間は、3.5時間×2×8=56時間
居宅で1名に対して月に2回、8件に対して診療
2,100点 × 1× 2× 8=33,600点
1件当たり所要時間は、20分×1=20分
準備等で30分かかると見積もれます。
総所要時間は、0.5時間×2×8=8時間
月の合計点数は、
93,600点+172,800点+33,600点=300,000点
所要時間は、
28時間+56時間+8時間=82時間
このように、1日の半分を訪問診療に割くことで、売上300万を達成することも不可能ではありません。
また、上記は歯科医師だけの算定で、歯科衛生士がいることで算定できる訪衛指などは含んでいません。歯科衛生士の訪問も含めると、300万の売り上げに達するまで、少ない時間で早く到達できることでしょう。
このような訪問を週4〜5回、午後のみ、複数施設に対して行えば、月300万円の収益構造は決して非現実的ではありません。
ポイントは「個人」ではなく「ルート」で設計すること
外来では「患者1人あたりの単価」で利益を計算しますが、訪問診療では「1施設」「1ルート」単位で収益を見積もることが重要です。
つまり、
- 1施設に何人の患者がいるか
- どの点数を、どの頻度で算定できるか
- それをどの曜日にルート化するか
を組み合わせることで、1ルート=1日あたりの収益モデルが完成します。
このルートを曜日ごとに固定し、担当チーム(歯科医師・歯科衛生士・コーディネーターなど)と連携することで、外来とは異なる“高密度・高安定”の診療体制が実現できます。
実例:月300万円を達成している医院の構造
たとえば、A医院では次のような運用をしています:
- 月〜金の平日すべて訪問診療に割り当て
- 訪問先は、特養2施設+グループホーム2施設+在宅1ルート
- 1日あたり平均8〜10名を診療
- 歯科医師1名+歯科衛生士1〜2名+運転・記録を担当するスタッフで構成
結果として、
1日あたりの点数:平均9,000点〜11,000点
月20日稼働で約18万〜22万点(=180万円〜220万円)
これに加えて処置や歯冠修復及び欠損補綴の算定等でさらに上乗せ
こうした積み上げにより、月300万円という収益が仕組みとして安定的に生まれるようになっているのです。
訪問診療は、特殊なことをしなくても「丁寧に計算された診療設計」と「確実な実行」によって、高い安定性と収益性を実現できます。
次章では、こうした安定収益を支える前提となる「仕組み化」に焦点を当て、成功医院が最初の3か月でどのような準備を行ったのかを具体的にご紹介します。
4.成功医院の共通点:最初の3か月で“仕組み化”に全力を注ぐ
鍵を握るのは「最初の3か月」
訪問診療で安定した成果を出している医院には、いくつかの共通点があります。その中でも特に際立っているのが、「最初の3か月間で、どこまで仕組みを整えられるか」に集中しているという点です。
この「最初の3か月」をどう過ごすかで、その後の診療の流れ、チームの動き、収益の安定度が大きく変わってきます。本章では、成功している医院が最初の段階でどのような準備をしているのかを、具体的に解説していきます。
スタート時は「件数」よりも「仕組みづくり」が優先
訪問診療を始めたばかりの時期にありがちなのが、「とにかく患者数を増やそう」という考え方です。しかし、成功している医院ほど、この時期は“件数を追わず、仕組みを整えること”に集中しています。
たとえば、A医院では最初の3か月間を「試運転期間」と位置づけ、以下のような準備を徹底しました。
スケジュールと役割分担を最初に固定する
最初に整えるべきは、「誰が」「どの曜日に」「どこに行くか」を決めた基本ルーティンです。
月曜日:施設A(定員30名)
火曜日:在宅エリア①(3名)
水曜日:施設B(グループホーム)
木曜日:在宅エリア②
金曜日:空き予備日または新規相談対応
このように曜日とルートを固定化することで、スタッフ間の連携が取りやすくなり、スケジュールの可視化・共有もスムーズになります。
加えて、歯科医師・歯科衛生士・コーディネーター(または運転・記録補助スタッフ)それぞれの役割を明確に分担することも、現場の混乱を防ぐ大きなポイントです。
書類・同意書・初期説明資料のテンプレート化
訪問診療では、診療そのもの以上に、「事前の説明」「同意取得」「記録」が重要です。
これらを毎回ゼロから作るのではなく、最初からテンプレートとして整備しておくことで、事務的負担を大幅に軽減できます。
具体的には:
- 訪問診療開始にあたってのご案内文(家族向け)
- 同意書・居宅療養管理指導の契約書
- 口腔内スクリーニング用チェックシート
- 医科や施設看護師と連携するための診療情報提供書
こうした書類を整えておくことで、トラブル予防だけでなく、施設や家族の信頼獲得にもつながります。
レセコン入力・算定チェックのW体制
訪問診療は算定ルールが複雑で、請求の“抜け漏れ”が収益を大きく左右します。
そのため、多くの成功医院では、開始時から「入力+チェック」のWチェック体制を敷いています。
初期入力は院内スタッフ(事務・コーディネーターなど)が行う
外部の歯科レセプト点検業者と連携し、算定ミスや漏れを定期的に確認する
こうした体制を最初から整えることで、月ごとの点数に安定感が出てきます。“訪問はやっているが売上が不安定”という医院の多くが、ここでつまずいているのが実情です。
医科・施設との連携体制も“段取り”が決め手
訪問診療では、歯科だけで完結せず、医科や施設職員との連携が欠かせません。
最初の段階で「どのように報告するか」「指示書のやりとりは誰が行うか」「緊急時の連絡体制」などを決めておくことで、現場の混乱を防げます。
また、訪問初回時に、診療内容だけでなく“姿勢”や“考え方”を伝えることで、信頼関係が構築されやすくなります。
訪問先にとっても「この医院はちゃんとしている」という安心感につながるのです。
まとめ:3か月間の“助走”が、3年後の安定をつくる
訪問診療の導入は、急いで拡大しようとするとかえって現場が混乱し、収益化が遅れがちになります。
逆に、最初の3か月間を「仕組みづくり」に専念し、ゆっくりでも丁寧に整備していくことで、後の展開がスムーズになります。
訪問診療は、地道に積み上げることで大きな成果を生む分野です。
そして、その積み上げを支える土台こそが、「最初の仕組み化」にほかなりません。
次章では、この仕組み化を継続的に支える「Wチェック体制」について、実例をもとにさらに詳しくご紹介していきます。
5.Wチェック体制で“請求漏れ”を防ぐ仕組み
訪問診療の次なる壁、「請求の精度」
訪問診療の運用が軌道に乗ってくると、次に浮かび上がるのが「請求の精度」という課題です。
診療は順調に進んでいるのに、思ったほど収益が伸びない。あるいは、レセプトの返戻が毎月のように発生してしまう――。その原因の多くは、診療報酬の「算定漏れ」や「算定ミス」にあります。
成功している医院の多くは、こうした事態を未然に防ぐために、「Wチェック体制」を導入しています。これは、訪問診療を“第2の診療室”として機能させるうえで欠かせない、静かなるインフラ整備とも言える取り組みです。
なぜ、訪問診療では請求ミスが起こりやすいのか
外来診療では、患者の診療内容がその場で完結し、レセコン入力も院内で即時に行われるため、比較的ミスが少なく済みます。
一方、訪問診療では以下のような背景から、請求の複雑化と見落としのリスクが高くなります。
- 施設単位での運用が中心となるため、個別の処置や対応が埋もれやすい
- 診療・記録・運転・対応を1チームでこなすため、入力や記録が後回しになりやすい
- 加算や制限の条件が複雑で、制度理解が不十分なまま運用されがち
たとえば、「歯科衛生士による居宅療養管理指導」が月4回まで算定可能であるにもかかわらず、2回しか請求されていなかったというケースや、「10人以上の単一建物診療」で本来ⅢであるべきところをⅡで算定していた、という事例もあります。
「Wチェック体制」とは何か
Wチェック体制とは、診療内容に基づくレセコン入力と、その確認・点検を別の担当者が行うという、二重の確認体制のことです。
「記録した人」と「確認する人」を分けることで、主観による見落としを防ぎ、返戻や算定漏れを最小限に抑えることができます。
Wチェック体制の具体的な運用例
第1段階:院内スタッフによるレセコン入力
診療当日または翌日に、訪問診療に帯同したコーディネーターや医療事務スタッフがレセコンに診療内容を入力します。
入力は、あらかじめ定めたマニュアルやテンプレートに基づいて行い、施設別・患者別の記録様式を活用することで、抜けや漏れを防ぎます。
「誰が・何を・いつ・どの施設で」行ったかを可視化できる記録シートを作成しておくと効果的です。
段第2階:点検担当者による算定内容のチェック
診療内容と請求点数の整合性を、医療事務の経験者や、歯科レセプト点検に詳しい外部スタッフが確認します。
この際に注目すべきポイントは、次のようなものです:
| チェック項目 | よくあるミスの例 |
| 加算の回数制限 | 月4回までの訪問歯科衛生指導料が5回分請求されている |
| 同一の建物に居住する患者数 | 実際は20人以上なのに歯訪4で算定されている |
| 居宅療養管理指導料の上限 | 歯科医師・歯科衛生士ともに月2回まで |
| 処置内容の算定要件 | 簡単な処置でも算定可能な点数が請求されていない |
| 交付 | 居宅療養管理指導重要事項説明書を患者又はその家族に対して交付していない |
このように、制度に精通した第三者の視点を入れることで、見落としの防止と収益の安定化が図れます。
外部パートナーの活用も有効
すべてを院内で完結するのが難しい場合には、歯科に特化した医療事務支援会社や点検支援サービスを活用する方法もあります。
あくまで「レセプト請求を代行する」のではなく、入力支援・点検補助・アドバイスを受ける形で連携するのが適切です。
これにより、限られた人的リソースでも高精度な請求体制を構築でき、スタッフの心理的負担も軽減されます。
請求精度の高さが、経営の安定をもたらす
訪問診療における請求業務は、単なる事務処理ではなく、医院経営の信頼性を支える重要な“基幹業務”です。
- 正確な請求ができている医院は、月々の収益が予測可能になり、次の戦略を立てやすくなる
- 入力・点検の体制が整っていれば、スタッフ間の連携もスムーズになり、ミスやトラブルが減る
- 医科や施設側から見ても、対応が的確で信頼できる歯科医院として評価される
このように、Wチェック体制は単に請求の的確さを高めるだけでなく、医院全体の信頼性と持続性を支える仕組みなのです。
次章では、このような“仕組み”の整った医院が、外部との信頼関係――とりわけ医科や施設との関係構築をどう実現しているのかをご紹介します。
6.医科や施設との信頼関係が“紹介”と“継続”を生む
成果を生む医院の信頼構築術
訪問診療の安定運営において、単に患者数を確保するだけでは十分ではありません。
本当に大切なのは、医科や介護施設との信頼関係をどう築くかという点です。
なぜなら、訪問歯科は「患者と医院」だけの関係ではなく、“地域のケアネットワーク”の一部として機能してはじめて継続的な診療が可能になるからです。
本章では、訪問歯科の成果を生み出している医院が実践している、対外的な信頼構築の具体策をご紹介します。
信頼される訪問歯科に共通する3つの特徴
医科や施設から「この歯科医院なら安心」と思ってもらえる医院には、いくつかの共通点があります。
1. 対応が早く丁寧である
初回訪問依頼に対して、48時間以内に訪問可否の返答をしている医院は、施設からの評価が高くなります。
初回訪問前には、診療内容だけでなく診療の流れ、説明のしかた、患者への配慮まで事前に資料化し、施設担当者と共有しています。
2. “報告”と“相談”がきちんとしている
医科の主治医や看護職員に対して、毎回の処置報告や経過説明を定期的に行うことが信頼につながります。
「診療して終わり」ではなく、他職種との連携を大切にしている姿勢が、次の紹介や長期継続へと結びついていきます。
3. “領域を侵さない”距離感を保っている
医科の主治医が介入すべき範囲には決して踏み込まず、「歯科ができること・できないことを明確に伝える」ことが、施設や医科側からの信頼を獲得するうえで重要です。
「むし歯があります」と伝えるのではなく、「誤嚥性肺炎予防の一環として、口腔清掃と衛生管理を提案したい」という目的重視の伝え方が効果的です。
成果を上げている医院の“紹介”を呼ぶ仕組み
成功している医院では、「1件の訪問先から次の施設紹介が生まれる」仕組みができています。
たとえば:
- 施設職員向けに定期的な口腔ケア勉強会を実施し、信頼と理解を深めている
- 主治医との連携を文書・電話・口頭でこまめに行い、“歯科の介入で状態が改善した”という成功体験を共有
- 「歯科の存在が医科や介護にとっても役立つ」というポジティブな印象が、口コミや紹介というかたちで波及していきます
紹介は、広告よりも強力な営業ツールです。
信頼関係から生まれる紹介こそが、訪問診療の経営を最も安定させる要因になります。
信頼構築には「最初の1回」が勝負
多くの医院が見落としがちなのが、「訪問初回の印象で、その後が決まる」という点です。
最初の訪問時に、「準備不足」「書類不備」「説明があいまい」といった対応をしてしまうと、それだけで継続が難しくなることがあります。
そのため、成功医院では次のような準備を欠かしません。
- 施設職員向けの「訪問歯科の概要パンフレット」を事前に提出
- 家族宛ての説明用紙や同意書を施設側と共有し、段取りをスムーズに
- 主治医への事前連絡(診療計画の共有・指示書の依頼など)を徹底
最初の一歩を丁寧に踏み出すことで、信頼と継続の道が開かれるのです。
まとめ:信頼関係が「売り込まなくても依頼がくる」流れをつくる
訪問歯科の収益を支えているのは、1日に何人診るかという数字だけではありません。
本質的には、「誰と、どのような関係を築いているか」が、患者数・依頼数・紹介件数の“質と量”を決定づけます。
信頼関係を育てることは、決して特別なことではありません。
丁寧に対応し、誠実に報告し、相手の立場を尊重する――
その積み重ねが、「継続」と「紹介」が自然と集まる訪問診療体制をつくるのです。
次章では、こうした関係づくりの先にある「導入成功事例」をご紹介します。
外来からの転換に悩んでいた医院が、どのように訪問を第2の診療室として確立し、地域の信頼を得ていったのか。そのリアルな歩みを追っていきます。
7.導入事例に学ぶ:外来主体からの転換に成功した医院
順調な外来の陰にある“見えない不安”
「外来は順調。でも、この先もずっと今の体制でいけるのか…」
そう語ったのは、埼玉県で開業15年目を迎えたS歯科医院の院長先生でした。
日々の診療は滞りなく回っている。リコール率も高く、患者からの信頼も厚い。
しかし、スタッフの定着率、診療報酬の頭打ち、設備投資の限界など、目には見えづらい“成長の天井”を意識するようになっていたといいます。
この章では、S歯科医院が「第2の診療室」としての訪問診療をどう確立し、月200万円以上の新たな収益の柱を築いたのか、その歩みをたどっていきます。
スタートのきっかけは「1件の在宅依頼」から
S医院が訪問診療を始めたのは、ある既存患者の家族から「通院が難しくなったので、自宅に来てもらえませんか」と相談を受けたことがきっかけでした。
最初は手探り。往診バッグを揃え、移動用の車両を確保し、診療予約の合間を縫って、週1回の在宅訪問を始めました。
院長先生は当時を振り返り、こう話しています。
「まさか、この1件の依頼が、医院全体の転換点になるとは思ってもいませんでした。」
「副業」ではなく「もうひとつの診療室」として位置づける
S医院が大きく変わったのは、開始から3か月が経過した頃です。
施設からの新たな相談が入り始め、「このままの体制では応じきれない」と気づいたことが転機になりました。
そこから院長先生は、訪問診療を“空き時間の活用”ではなく、“第2の診療室”として設計し直すことを決断します。
具体的には:
- 月・水・金の午前は訪問専用にブロック化し、外来と完全に分ける
- 訪問担当歯科医師を1名採用(非常勤)
- 衛生士と記録担当の2名を訪問専属で配置
- 訪問対象施設をエリアごとに曜日固定でルート化
こうした体制変更により、医院全体の動きがスムーズになり、患者にもスタッフにも無理のない診療が実現しました。
安定収益の鍵は「スケジュール設計と点数管理」
導入から半年後には、訪問診療の収益は月100万円を超え、1年後には月200万円を安定して計上するまでになりました。
要因は、決して“患者数が多かった”ことではありません。
むしろ、ルート・点数・請求を戦略的に設計したことが、収益の安定を生んだのです。
S医院では、訪問1日あたりの目標点数を9,000点と設定。
施設ごとの患者数・算定可能な項目・必要な加算などをシミュレーションし、1ルート=1診療室とみなして運営していました。
また、Wチェック体制や書類テンプレートも早期に整備し、ミスによる返戻や未請求も最小限に抑えられています。
「信頼」が「紹介」を呼び、持続可能な循環が生まれる
S医院の成長を後押ししたもうひとつの要因が、施設・医科との関係づくりです。
- 訪問初回時には、施設職員全体向けの説明会を実施
- 医科の主治医とは診療内容を定期的に共有
- 家族への報告も丁寧に行い、信頼の輪が広がっていきました
その結果、訪問先施設から別施設の紹介が次々と舞い込むようになり、営業をかけなくても、訪問の枠は常に埋まる状態となったのです。
「ひとつの診療室を、地域の中にもうひとつ持つ」
S医院の取り組みを通じて見えてくるのは、訪問診療を単なる補完的な手段としてではなく、「地域にもう一つの診療室を持つ」こととして捉えた視点の重要性です。
外来のユニット数には限界があります。しかし、訪問診療という選択肢を戦略的に設計すれば、“医院の成長余地”を外部に拡張することができるのです。
まとめ:導入事例に学ぶ“転換”のヒント
S医院のように、外来主体の医院であっても、
- 訪問を「副業」ではなく「診療室」として位置づけ
- スケジュールと役割を明確化し
- 地域との関係性を育みながら拡張する
という道を取ることで、安定収益とスタッフの働きやすさ、そして地域からの信頼を同時に手に入れることができます。
訪問診療の導入は、医院にとって「何かを失う選択」ではなく、新しい診療室を得ることによる“拡張”なのです。
8.訪問診療は“未来への投資”である
成功のカギは、才能でも条件でもない
これまで7章にわたって、訪問診療を「第2の診療室」として位置づけ、安定収益と信頼を得ている医院の取り組みをご紹介してきました。
改めて振り返ってみると、訪問診療の成功には「特別な才能」や「恵まれた条件」が必要なわけではないことがわかります。
必要なのは、「正しく設計し、着実に仕組みをつくり、信頼を育む」という、一貫した姿勢です。
外来依存のリスクと、“もう一つの柱”の必要性
歯科医療を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。
- 外来患者の高齢化と通院困難の増加
- 人件費・材料費の高騰
- 診療報酬制度の変動による将来の不透明さ
こうした背景の中、「ユニットを増やす」「患者数を増やす」だけでは限界があることに、多くの医院が気づき始めています。
だからこそ、外来に次ぐ“もうひとつの柱”が必要とされているのです。
その答えのひとつが、訪問診療=第2の診療室の戦略的運営です。
訪問診療は“奉仕活動”ではなく、医院を支える経営戦略
訪問診療というと、「高齢者のため」「社会貢献」というイメージが強いかもしれません。
しかし、実際に成果を上げている医院の多くは、訪問を“経営戦略”として捉えています。
- スケジュール・役割・人材配置を整備し
- 算定項目と収益構造を見える化し
- 地域・施設・医科との信頼関係を構築しながら
- 継続と紹介の“自走する仕組み”をつくっている
このように、訪問診療は単なる「補完策」ではなく、医院の未来を守る“設計された経営モデル”として機能しているのです。
訪問診療は「小さく始めて、大きく育てる」ことができる
ここで取り上げた事例の多くは、いずれも小規模なスタートでした。
1件の在宅訪問から、1施設だけの訪問から――誰にでもできるスモールスタートです。
そこから、
- 曜日固定
- ルートの定着
- スタッフの専任化
- 請求体制のWチェック
- 地域連携の強化
といった“育てる工程”を経て、月100万、200万、そして300万円の安定収益を生み出す診療室へと進化していったのです。
訪問診療の最大の魅力は、この「成長余地」と「再現性」にあります。
「外来×訪問」の二本柱が、医院の未来を支える
今後、地域包括ケアがますます推進され、在宅医療の需要は増加の一途をたどります。
その中で歯科が果たすべき役割も、確実に拡大しています。
外来診療の強みを維持しつつ、訪問診療をもう一つの柱として育てることで、医院経営は「安定」と「社会的価値」の両立を実現できます。
訪問診療は、医院が“地域の中にもう一つの診療室を持つ”こと。
それは、地域社会とのつながりを深め、スタッフの働き方を広げ、未来の医院経営を支える確かな投資となるのです。
最後に
「訪問診療は難しい」「うちには無理だ」と感じる方こそ、本稿を通じて“しくみ”の大切さに気づいていただけたのではないでしょうか。
大切なのは、「どれだけ多くの患者を訪問するか」ではなく、
「どのように運営するか」「どのように続けられる仕組みをつくるか」です。
ぜひ、明日から一歩を踏み出してみてください。
それが、医院の未来を変える“第2の診療室”への入り口になります。
要約レポートPDFプレゼント
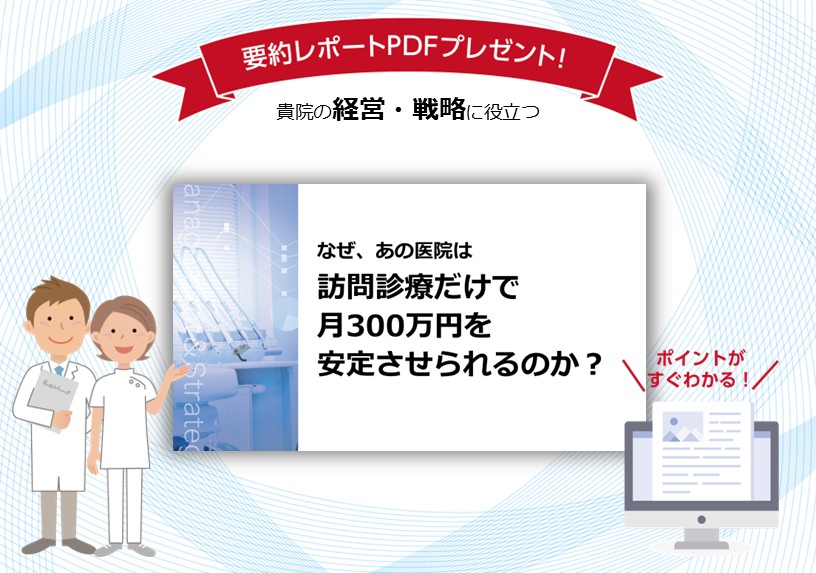
「外来診療だけではもう限界…」
そう感じていませんか?
実は、外来以外の時間を有効活用し、“第2の診療室”をつくるだけで、月300万円の安定収益を実現している医院があります。
このレポートでは、小規模スタートから収益を積み上げ、最短3か月で安定化させた成功ノウハウを公開。
さらに、算定ミスを防ぐ請求体制や、紹介につながる信頼構築の仕組みまで、実例を交えて解説しています。
もしあなたが、
- 外来の収益に限界を感じている
- 医院経営をもっと安定させたい
- 将来の成長基盤を今から築きたい
と考えているなら、このレポートは必見です。
今すぐダウンロードして、「訪問診療だけで月300万円を安定させる仕組み」を手に入れてください。
このレポートでわかること
- 訪問診療は“第2の診療室”
- 成功事例の実証
- 安定収益の仕組み
- 算定・請求の精度が利益を守る
- 信頼が“紹介”と“継続”を生む
- 経営と社会的意義の両立