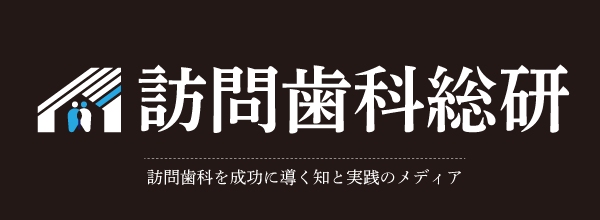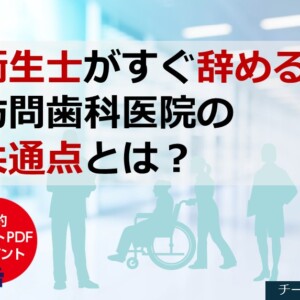「チームで回す」訪問診療 ― ロール分担と報酬設計
目次
1. なぜ今、「チームで回す」訪問診療が求められているのか?
歯科医院の経営環境は、今、激しく変化しています。人口減少、超高齢社会、人材難、後継者不足。こうした構造的な変化は、外来主体の運営モデルに限界をもたらしつつあります。
その中で、注目されているのが「訪問歯科診療」という選択肢です。ただし、ここで重要な点があります。それは「訪問診療を個人でやるか、チームでやるか」という根本的な運営スタイルの違いです。
「個人で回す」限界
訪問診療の初期導入では、多くの歯科医院が歯科医師単独、もしくは衛生士との2人チームでスタートします。移動から施設対応、治療、報告書作成まで一手に抱えるケースも少なくありません。
しかしこの運営形態では、やがて限界がやってきます。たとえば、こうした医院では診療時間の確保が困難になり、応急的な「フロー型」の訪問診療にとどまりがちです。結果として、安定収入にはつながらず、スタッフの疲弊も進みます。
「チームで回す」ことで初めて見える風景
一方、計画的・継続的な「ストック型」の訪問診療を実現している医院には、共通する特徴があります。それが、明確なロール分担と、チーム運営の仕組みを備えていることです。
歯科医師は医療行為に集中し、衛生士は予防ケアを担当する。運転や施設との折衝、請求や文書処理は事務スタッフが担う。それぞれの専門性を活かしながら、組織として効率的に回すことで、1日の診療効率も大きく向上します。
さらに重要なのは、こうしたチーム体制が報酬設計とも深く関係していることです。誰がどこまでの責任を持ち、どの成果にどう貢献したのか。それが見えるからこそ、評価も正しく分配され、スタッフの納得や定着率向上にもつながるのです。
チーム運営=「仕組み化」の核心
つまり、「チームで回す訪問診療」とは、単に役割分担することではありません。医院の持続可能性を高め、将来の成長を見越した戦略的な「仕組み化」なのです。
ストック型の訪問診療は、数カ月先の報酬を見通すことができるモデルです。だからこそ、投資も、採用も、教育もできる。歯科医師が孤軍奮闘せずとも、医院全体で成長を支える土台をつくることができます。
本稿では、第2章以降で「職種ごとの役割と動き」「ロールごとの評価と報酬設計」「事例紹介」など、実務的な視点からチーム運営の要点を掘り下げていきます。
次章では、訪問診療を支える5つの基本職種とその連携の全体像について見ていきましょう。
2. 訪問診療チームの全体像 ― 5つの基本職種とその関係性
訪問歯科診療の現場では、しばしば「誰が、どこまで、どのように関わるのか」が曖昧なまま、現場任せで運営が行われています。結果として、負担が偏ったり、作業の抜け漏れが発生したりするケースも珍しくありません。
では、持続可能で高効率な訪問診療を実現するには、どのような職種構成が必要なのでしょうか。本章では、訪問診療をチームで支える「5つの基本職種」の役割と、相互の関係性について解説します。
1.歯科医師:医療判断と処置の中心を担う
歯科医師の主な役割は、診断、治療方針の決定、麻酔・抜歯・充填などの医療行為です。特に訪問診療においては、限られた時間と設備のなかで、的確な判断が求められます。
また、同席する介護職員や家族、時にはケアマネジャーとのコミュニケーションも重要な業務のひとつです。説明責任を果たしながら、現場での信頼を獲得することが、スムーズな診療環境をつくります。
ただし、移動手配や機材準備、報告書の作成といった周辺業務にまで関与していては、本来のパフォーマンスが発揮できません。歯科医師が「診ること」に集中できる環境を整えるのが、チーム制の意義といえるでしょう。
2.歯科衛生士:口腔ケアと継続管理のプロフェッショナル
衛生士は訪問診療において、極めて重要な役割を果たします。口腔清掃、歯周病予防、リハビリ支援、さらには患者の生活背景に寄り添った対応まで、まさに現場の要です。
『歯科訪問診療-他職種連携、必携器具から算定まで』でも指摘されているように、訪問診療の評価は「治療行為」よりも、「継続的な口腔管理」に重きが置かれる時代へと移行しています。衛生士の技術と観察眼が、患者の状態変化を早期に察知し、重症化予防につながるのです。
3.事務スタッフ:影の司令塔として情報と請求を支える
訪問診療における事務スタッフの役割は、外来以上に多岐にわたります。診療スケジュールの調整、ケアマネとの連絡、文書作成、保険請求業務…。いずれも、診療の質を支える“縁の下の力持ち”です。
特に介護保険を含むレセプト請求は複雑で、医院内でWチェック体制を取らなければ、算定漏れや返戻のリスクが高まります。チーム全体の“請求精度”を高めるために、事務の仕組みづくりは極めて重要です。
4.運転・同行支援スタッフ:現場到達の安全と効率を担保する
訪問診療では、移動そのものが業務の一部です。渋滞や道順の把握、駐車の確保、さらには機材の運搬補助までをスムーズに行えるかどうかで、1日の診療効率は大きく左右されます。
また、高齢施設や自宅への訪問時には、患者や家族に「安心感」を与えるマナーや所作も大切です。スタッフの印象は、そのまま医院全体の評価に繋がるからです。
5.施設・介護側との連携担当:信頼を築く“交渉役”
訪問診療において、施設側との調整を担う役割も欠かせません。診療スケジュールの調整、同意書の回収、口腔状態の報告など、信頼関係を築く上で欠かせない業務が多々あります。
とりわけ初期導入期には、ケアマネジャーや施設長との関係構築が、今後の集患や継続診療の成否を左右します。誰がこの役割を担うかは医院によって異なりますが、明確な「窓口担当者」を設定することで、信頼性が格段に高まります。
補足:1人が複数役を担うことも可 ― ただし、ルールと共有が前提
もちろん、小規模な歯科医院では、1人が複数の役割を担うこともあります。重要なのは、「誰が何を、どこまで担うか」を文書化し、共有しておくことです。属人的な運用では、必ずどこかで破綻します。
次章では、これらの職種が「いつ」「どのように連携するのか」を、1日の診療スケジュールを追いながら、具体的にご紹介していきます。
3. 1日の流れで見る「理想のチームワーク」
チームで訪問診療を運営するうえで、もっとも分かりやすく機能を確認できるのが、「1日の流れ」を時系列で追うことです。本章では、午前から午後にかけて2〜3施設を訪問する標準的なスケジュールをもとに、職種別の連携ポイントを解説します。
8:30 出発準備 ― スタート地点は「院内の連携」から
朝の始動は、院内での準備から始まります。前日までに事務スタッフが作成した訪問スケジュール表をもとに、当日の患者リストや同意書、連絡事項などを最終確認します。
- 歯科医師・衛生士は、使用予定の器具・材料の準備や滅菌チェック。
- 事務スタッフは、訪問対象者の保険状況・公費番号の確認と、施設への事前連絡。
- 同行スタッフは、車両・ナビ設定・駐車スペースの確認など移動準備を行います。
この時点で情報の齟齬や準備漏れがあると、現場でのトラブルにつながるため、朝の5分ミーティングが有効です。
9:00 出発・移動 ― トラブルを未然に防ぐ「運転管理」
訪問先までの移動は、単なる“移動”ではなく、安全運行と時間厳守を実現する「業務」です。特に高齢者施設は訪問時間が厳格に決まっている施設では、遅延は信頼を大きく損ないます。
運転スタッフがいない医院では、衛生士や歯科医師が兼任することもありますが、その場合も運転中の連絡対応やナビ操作を誰が担うかを事前に決めておくことが肝要です。
9:30〜11:30 診療 ― それぞれの役割が明確に機能する時間帯
診療時間は、まさにチームワークの真価が問われる時間です。
- 歯科医師:診察と治療、診療計画の立案、施設職員への説明。
- 歯科衛生士:口腔ケアやスケーリング、摂食・嚥下のチェック、患者対応。
- 同行スタッフ:診療準備や機材受け渡し、終了後の片付け補助。
- 施設連携担当:口腔ケアの報告書提出、職員からの要望ヒアリング、次回日程調整。
また、記録文書の下書きやレセプト用のメモも、診療の合間に進めておくと、帰院後の事務作業が大幅に短縮されます。
12:00 移動・昼食 ― 合間にも「調整業務」は進行中
移動時間や昼食の時間にも、チーム内の情報共有や次の施設への確認電話などを行います。たとえば事務スタッフが医院から電話で確認対応を行い、現地チームにリアルタイムで伝達するといった連携が可能です。
13:30〜15:30 午後の診療 ― 疲労と集中力の管理がカギに
午後の診療は、午前の疲労がたまり、集中力が途切れがちになる時間帯です。そのため、診療時間と休憩のバランスを意識したスケジューリングが重要です。
また、午後の施設は医療的ケアが必要なケースもあり、リスクが高い場面に備えて「役割分担の徹底」が求められます。医療判断、記録、施設職員対応を並行して行うことがあるため、W対応体制の準備が必要です。
16:00 帰院・片付け・記録 ― “診療の終わり”は“次回への準備”
医院に戻ったら、まずは使用済み器具の滅菌処理と記録類の整理です。
- 歯科医師・衛生士:電子カルテや記録書類の入力、次回診療のオーダー確認。
- 事務:保険・介護のレセプト準備、診療報告書の送付、施設へのお礼連絡。
- 運転スタッフ:車両の整備・消毒・次回準備。
この時間帯に「次回訪問への布石」を打っておくことで、チーム全体の回転力が高まります。
チーム全員が“診療を回している”という意識
1日の流れを見ても明らかなように、訪問診療は「歯科医師が診る」だけで成り立つものではありません。むしろ、事前準備、現場対応、記録・請求といった周辺業務を誰がどのように担うかが、医院の生産性と品質を左右します。
次章では、このような連携を“持続可能な制度”として形にするための、ロール別の報酬設計と評価の考え方を掘り下げていきます。
4. ロール別の報酬設計と評価の考え方
チームで訪問診療を回すためには、明確な役割分担と同時に、それぞれの役割に応じた報酬設計が必要です。
単に人を「配置する」のではなく、納得して動いてもらうための制度設計こそが、訪問診療の仕組み化には欠かせません。
なぜ、報酬設計が重要なのか?
訪問診療に携わる職種は、それぞれ異なる貢献の仕方をしています。
- 歯科医師は診断と治療の中心的役割を担う。
- 衛生士は日々の継続ケアを通じて患者満足度とLTVを高める。
- 事務は請求精度や収益性を影から支える。
- 運転・同行スタッフは、スケジュールの遅延や現場混乱を未然に防ぐ。
- 施設との窓口役は、新患紹介や継続依頼の起点となる。
それにもかかわらず、「一律の時給」「固定の手当」で評価されていては、やる気と定着を維持することは困難です。
【基本原則】「業務量」×「専門性」×「成果」=報酬評価の3軸
報酬設計においては、以下の3軸で評価する考え方が有効です。
- 業務量(時間・回数・件数)
→ 診療同行回数、記録件数、処置数など。 - 専門性(資格・スキル)
→ 歯科衛生士免許の保有、摂食・嚥下の認定資格など。 - 成果(医院への貢献度)
→ 新患紹介件数、LTVへの寄与、離職防止、請求精度向上など。
たとえば、衛生士が1件の訪問で処置と指導、記録まで完結した場合には、「1回○円」の出来高制も検討できます。あるいは、件数に応じて段階的にインセンティブを加算する設計も現実的です。
【職種別】報酬設計の一例
● 歯科医師
- 固定月給 or 診療売上の○%(業務委託型)
- 加算算定数によるインセンティブ(例:在歯管10件以上で月1万円)
● 歯科衛生士
- 同行1件ごとの手当(例:1件1,000円+記録1件500円)
- 週訪問回数に応じた加算(例:週5回で月5,000円の手当)
● 事務スタッフ
- レセプトエラーゼロ達成で月額手当
- 新規訪問導入時の届出・同意書業務を定額報酬で加算
● 運転・同行支援スタッフ
- 半日単位の固定手当(例:午前帯3,000円)
- 渋滞・駐車対応が発生した場合の特別手当加算
● 施設窓口担当
- 新患紹介件数に応じた成果手当(例:紹介1件あたり1,000円)
- 契約施設数ごとの段階加算(例:10施設達成で+月1万円)
モチベーションを支える“見える化”の工夫
報酬制度は「見える化」することで、さらに意味を持ちます。
月ごとの役割実績を表やグラフでチーム全体に共有することで、自分の貢献が数値として可視化され、モチベーションが高まります。
また、ミーティングでの称賛や表彰制度も取り入れることで、報酬以上の満足を感じられる職場になります。
報酬制度が「辞めないチーム」をつくる
報酬設計は、単なるお金の話ではありません。
適切に評価されているという実感こそが、離職防止の鍵となります。
実際、仕組み化された訪問診療チームをもつ医院ほど、衛生士や事務スタッフの定着率が高く、「人が辞めない組織」になっている傾向があります。
次章では、こうした制度や分担をよりスムーズに浸透させるために不可欠な、「見える化」と教育の工夫について詳しく解説していきます。
5. “見える化”で生まれるチームの納得感と成長力
いかに理想的なロール分担や報酬設計が整っていても、それがスタッフに伝わっていなければ意味がありません。
また、制度が「誰の目にも分かる」形で可視化されていなければ、スタッフは自らの役割や貢献を実感することができず、やがて不満や疑念が生じます。
チームで訪問診療を運営するうえで、“見える化”と教育の仕組みは極めて重要な基盤となります。
「見える化」とは何か?
ここで言う“見える化”とは、単なる掲示やグラフ化にとどまりません。
以下の3つのレベルで情報を整備・共有することが重要です。
1. 業務の“見える化”
- 各職種の業務フローや分担表を明文化
- チェックリスト化・標準作業手順書(SOP)の整備
- 例:歯科衛生士の「1訪問で行う処置一覧チェック表」
2. 成果の“見える化”
- 月間訪問件数や加算算定数などをグラフで共有
- チーム別・個人別の達成目標の進捗表示
- 例:訪問件数ベスト3のスタッフを掲示・表彰
3. 報酬の“見える化”
- インセンティブの算出根拠を明示
- 「自分が何をすればどう評価されるのか」がわかる設計
- 例:1人あたりの平均訪問回数×単価=貢献度として月次提示
「可視化された役割」が納得を生む
業務分担を口頭で伝えるだけでは、時間が経てば曖昧になり、「それ、私の仕事じゃないと思ってました」という事態にもなりかねません。
たとえば、事務が「患者情報の前日確認と印刷」を担うのか、「衛生士が朝に確認して自分で出す」のか。
このような細かいタスクも担当と責任範囲を一覧表にして見せることで、曖昧さを解消できます。
納得のあるロール分担とは、「不満が出ない」ことではなく、「納得できる根拠がある」ことです。
教育制度は“仕組みの種まき”
スタッフの質は、医院の訪問診療の質そのものです。
そこで重要なのが、“教育の仕組み化”です。
● 導入教育の整備
- 新人向けマニュアル(役割別)
- OJTの進行チェック表(例:1週間目/1カ月目でクリアすべき業務)
● スキルアップ支援
- 月1回の院内ミーティングでのケース共有
- 加算算定・制度改定に関する勉強会(オンライン視聴でも可)
● 教育係の配置
- 職種ごとの教育担当(例:衛生士リーダーが実地同伴)
- 評価者を分けることで公平性を確保
教育は一過性ではなく、「成長できる場」としての継続がカギです。
現場の声を拾う“ミニ・カイゼン”制度
「現場で感じた小さな違和感」ほど、仕組みを良くするヒントはありません。
たとえば以下のような制度を導入すると、チームの成熟度が高まります。
- 診療後5分で記入する「現場ふりかえりメモ」
- 月1回の「改善提案カード」提出と採用時の表彰
- 朝礼での1分スピーチ(現場の“良い工夫”をシェア)
こうした仕組みが、単なる“スタッフ”を“医院の仲間”へと育てていくのです。
人が辞めない組織は、「伝わる仕組み」を持っている
訪問診療は「個」の努力では回りません。
だからこそ、仕組みとして“伝わること”が続く力になります。
- 役割が明確で、評価される。
- 自分の成長が見える。
- チームの貢献が称賛される。
こうした文化が、やがて“辞めない医院”をつくります。
次章では、こうして育てたチームが、どのように「制度」に強くなり、算定や加算の獲得に貢献する仕組みを持つかを解説します。
訪問歯科診療を“収益事業として安定化”させるための要となる章です。
6. 制度に強いチームが医院を伸ばす理由
訪問歯科診療は、現場での対応力と同じくらい、「制度に対する理解力」が成果を左右します。
特に保険請求や加算算定の精度は、医院の収益に直結するだけでなく、チーム全体の成熟度を示す指標でもあります。
本章では、制度対応力を持つチームをどう育て、仕組み化するかに焦点を当てます。
制度に弱いチームが陥る“3つの罠”
訪問診療を始めたばかりの医院や、ロールが曖昧な組織では、以下のような問題が頻発します。
- 加算の算定漏れ
→ 対象患者であるのに、届出や文書が整っておらず算定できない。 - 記録不備による返戻・減点
→ 同意書・報告書の不備、レセプト記載の誤りなど。 - 制度改定への対応遅れ
→ 点数の変更や新設加算へのアンテナが立っていない。
これらの問題の背景には、「制度が特定の個人だけに依存している」状態があり、誰かが辞めた瞬間に医院の制度対応力がゼロになるというリスクがあります。
制度対応は「チームの仕事」として仕組み化せよ
制度に強い医院では、チーム全員が“加算取得の重要性”を理解し、実務レベルで分担できています。
たとえば:
| 加算・制度名 | 担当職種 | 役割例 |
| 歯在管(在宅患者歯科管理料) | 歯科医師・衛生士 | 初診時の管理計画、継続的な管理の実施 |
| 居宅療養管理指導(介護保険) | 事務+医師(記録) | レセプト記載、文書作成 |
| 同一建物・複数名訪問の算定 | 事務 | 対象患者の抽出、日程調整、施設連絡 |
| 情報提供文書関連(医科・施設) | 事務・窓口担当 | 必要文書のフォーマット準備、送付、控え管理 |
このように、誰が、いつ、何をして、何を残すかが決まっていれば、制度に対する耐性は一気に高まります。
Wチェック体制で“請求精度”を最大化する
訪問診療の請求には、医療保険+介護保険の二重構造が存在します。
そのため、レセプト入力と請求管理は必ず“Wチェック体制”で運用すべきです。
[Wチェックの一例]
- 一次入力:事務スタッフ
→ レセコン入力、介護レセプト作成、診療内容の確認 - 二次チェック:外部委託 or 院内ダブルチェック
→ 算定漏れ・記載ミスの発見、対象外加算の有無チェック
この体制によって、月単位での返戻ゼロ・加算取得率の向上が現実的に目指せます。
制度対応を支える“院内ナレッジ”の整備
制度対応を属人化させないためには、院内マニュアルとナレッジの整備が不可欠です。
- 加算ごとの「算定条件・流れ・担当」一覧表
- 新算定項目・加算発表時の「対応フロー」(例:複訪の導入手順)
- レセプト記載フォーマット・過去の返戻事例ファイル
これらは「次に入ったスタッフ」への教育にも使えるだけでなく、組織の対応スピードを上げ、制度変更のたびに右往左往する状態を脱却できます。
制度に強い医院は、紹介と信頼を生む
制度に明るいチームは、施設・ケアマネ・医科との信頼構築にも有利です。
- 「あの歯科医院は文書がきっちりしている」
- 「家族への報告が丁寧」
- 「保険のこともよく分かっていて安心」
こうした評判が、新患紹介や継続依頼につながります。
次章では、こうして制度対応力を高め、チーム運営を仕組み化した結果として得られた成功事例をご紹介します。
「人が辞めない医院」「継続的に件数が伸びる医院」は、何をしていたのか。その秘密に迫ります。
7. 成功事例:多職種が自律的に動く医院の仕組み化
「訪問診療は個人戦ではない」――この考えのもと、組織全体で仕組みを整えた歯科医院が、現場の負担を軽減しながら訪問件数と定着率を同時に高めることに成功しています。
本章では、実際にチーム運営を軸にした仕組み化に取り組み、大きな成果を上げた2つの医院を紹介します。
事例①:院長が現場に出なくても回る体制に成功(S歯科医院/千葉県)
課題:
S歯科医院では、院長が訪問診療を全て担っており、週3回は午後の外来を閉めて対応していました。
患者数は安定していたものの、院長の疲弊と事務処理の遅延が深刻化し、これ以上の拡大ができない状況に陥っていました。
取り組み:
- 診療同行を歯科衛生士主体の2人体制に変更し、医師の訪問は週1回に縮小。
- 訪問先の施設対応、日程管理、報告書対応を事務スタッフが主導。
- 訪問の記録・連携情報はGoogleスプレッドシートで全員が共有。
- 医院全体の月1ミーティングで「診療・請求・対応」全体を見直し。
結果:
- 院長の訪問時間を70%削減しながらも、訪問件数は月30件→月50件へ増加。
- 歯科衛生士が「主体的に提案する体質」に変化し、離職ゼロを継続中。
- 事務と衛生士でWチェックを行う請求体制が整い、算定漏れがほぼゼロに。
事例②:衛生士主導のチーム制でLTVが2.3倍に(Tデンタルクリニック/愛知県)
課題:
訪問診療をスタートして2年目。応急処置の連続となり、1件ごとの報酬が少なく、事業としての採算が合っていませんでした。
また、スタッフも「やらされ感」が強く、離職の不安もありました。
取り組み:
- 訪問業務を“4つのロール”に分類(診療、衛生ケア、施設連携、請求)。
- 衛生士に「摂食嚥下リハ」や「口腔ケア」の研修機会を提供。
- 施設への報告文書を衛生士が作成し、ケアマネとの連携のハブに。
- LTV(1患者あたりの生涯訪問単価)を月次で可視化・共有。
結果:
- 1患者あたりの平均訪問回数が2.7回→6.1回に。
- 訪問LTVは約12万円→約28万円へと2.3倍に増加。
- 施設からの紹介が自然発生的に増え、集患にほとんど営業を要しなくなる。
共通点:制度と現場が“つながっていた”
両医院に共通するのは、「業務」「制度」「評価」のすべてがバラバラではなく、連動していた点です。
| 仕組み要素 | 成果に結びついた要因 |
| ロール分担 | 歯科医師・衛生士・事務・同行が明確に分業 |
| 報酬設計と見える化 | 役割に応じた評価と成果の数値化 |
| 請求と記録の制度化 | Wチェック体制とナレッジ共有 |
| 教育の仕組み | 定着率向上と役割進化(衛生士が施設連携まで担う) |
チームは“機能”するから続く
人が辞めない、収益が安定する、紹介が増える――
これらは偶然ではなく、「チームが機能する仕組み」を整えた医院が手に入れている必然の結果です。
次章では、ここまでの要点を総括しながら、「訪問診療の未来と医院経営の可能性」について展望を述べていきます。
8. まとめ:訪問診療は“未来への投資”である
ここまで7章にわたり、訪問診療を「チームで回す」ための視点と仕組みを紐解いてきました。
歯科医師が一人で背負うのではなく、全員が機能するチームを構築すること。それが、持続可能な訪問診療の本質です。
「チーム制」こそが医院の“もうひとつの成長エンジン”
訪問診療を取り入れた医院では、「外来の補完」ではなく、独立した第二の診療室=もうひとつの収益軸として成長するケースが増えています。
- 外来ではアプローチできない患者層へリーチできる
- 高齢化とともに需要は確実に増加する
- 予測可能な報酬モデルで経営の安定に貢献する
しかもこれは、単なる収益獲得の手段ではありません。
訪問診療を通じて医院は「地域の医療・福祉ネットワークの一員」となり、地域から選ばれる存在へと進化していくのです。
“属人診療”から“仕組み診療”へ
訪問診療の未来を切り開くカギは、「人ではなく、仕組みで診療を回す」ことにあります。
- 誰かが辞めても回る体制
- 人が育ち、残る環境
- 業務が明文化され、共有される組織
こうした医院は、成長と安定を両立させることができます。
逆に、“頼れる一人”にすべてが依存する医院では、どれほど技術があっても継続は困難です。
未来に向けて ―「訪問診療=経営戦略」の視点を持つ
訪問診療は、決して“福祉的なおまけ”ではありません。
今や、明確な経営戦略の柱として位置づけられるべき分野です。
特にこれからの時代、「患者数は減るが、ニーズは濃くなる」。
こうした構造的変化に柔軟に対応できる医院だけが、生き残り、選ばれていくのです。
今、第一歩を踏み出す医院へ
本稿でお伝えしてきた「チーム制訪問診療」は、最初から完璧な形で整える必要はありません。
重要なのは、「属人的にならないように分ける」ことと、「共有と見える化の文化を育てる」ことです。
- 小さく始めて、定着させる
- 回してみて、改善する
- 担当を持たせて、任せてみる
このように、小さな仕組みを積み重ねることが“本物のチーム”を育てる道なのです。
要約レポートPDFプレゼント
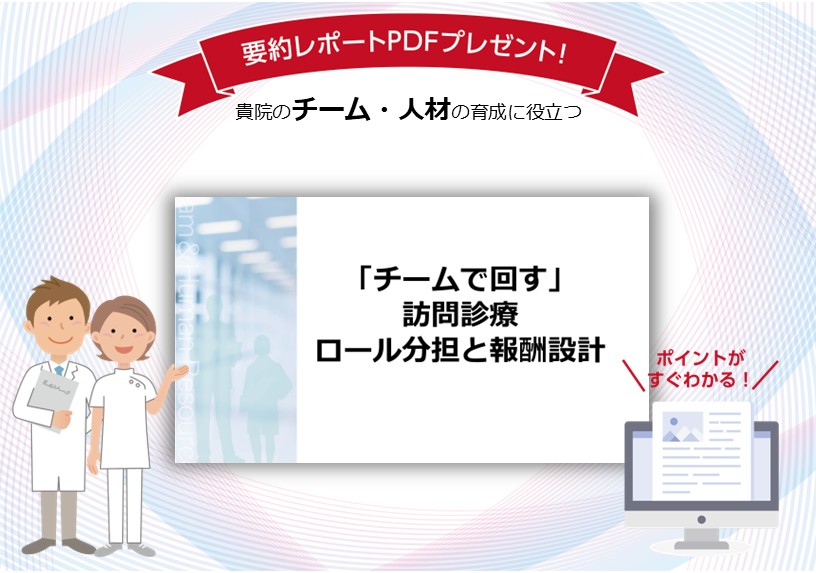
「院長ひとりで背負う訪問診療はもう限界…。
離職ゼロ・収益安定・診療品質向上を同時に叶える“チーム運営の仕組み”を知っていますか?」
本レポートでは、訪問診療をチームで回すためのロール分担と報酬設計の全体像を徹底解説。
- 診療効率と品質を高める5職種の役割
- 公平で納得感ある評価制度のつくり方
- スタッフの離職を防ぐ“見える化”の仕組み
- 成功事例に学ぶ、医院経営の安定と拡大戦略
「チーム制を導入した結果、訪問件数アップ・LTV向上・離職ゼロを実現」──そんな成果をもたらす実践知が詰まった1冊です。
今すぐダウンロードして、あなたの医院経営を次のステージへ。
このレポートでわかること
- 個人運営の限界とチーム運営の必要性
- 5職種による訪問診療の最適運営
- 公平で透明な評価・報酬設計
- 制度対応力とナレッジ共有の重要性
- 成功事例と成果